コロッセオ

円形劇場はラテン語でアンフィテアトルム・フラウィウム(Amphitheatrum Flavium)、イタリア語では単にアンフィテアトルム(Anfiteatro)と呼ばれる。 世界最大のローマ円形劇場であり、収容人数は5万から8万7千人と推定される。これはローマで最も壮観な円形劇場の中心に位置し、同時に現代に伝わる古代遺跡の中でも最も印象的な遺構である。
1980年にはローマ歴史地区全体、イタリア国内の教皇庁領、聖パウロ大聖堂とともにユネスコ世界遺産に登録された。その後2007年には、ニュー・オープン・ワールド・コーポレーション(NOWC)主催の「新世界七不思議」投票で選出されている。 フラウィウス朝時代にローマ・フォロム東端の土地に建設されたこの円形闘技場は、西暦70年にウェスパシアヌス帝によって着工され、ティトゥス帝によって完成。同帝は西暦80年4月21日に開館式を執り行った。その後、ドミティアヌス帝の治世下で若干の改修を経て、西暦90年に最終的な完成を迎えた。
歴史の視点
フラウィウス朝の皇帝ウェスパシアヌスによって紀元70年から72年に着工され、当時の他の公共事業と同様に、属州からの税収と、紀元70年のエルサレム神殿略奪による戦利品によって賄われた。 建設地はヴェリア丘、オッピオ丘、チェリオ丘に囲まれた窪地に選定された。この地には詩人マルティアルが「スタグヌム」と呼んだ人工湖(ネロが黄金宮殿のために掘らせた)が存在した。この池、あるいは水域は、チェリオ丘のクラウディウス神殿基部から湧く泉によって供給されていた。 ウェスパシアヌスは、暴君の政策を覆す償いの事業としてこれを隠した。ネロは公有地を私物化し、統治形態において前例と後世を示す存在であった。ウェスパシアヌスは水道橋を公共利用に転換し、湖を復元、観客席(カヴェア)の基礎を強化した。
79年に死去する前に、ウェスパシアヌスは最初の2層の完成を監督し、構造物の開会式を成功裏に執り行った。 これはユリウス・クラウディウス朝時代の小規模あるいは仮設的なもの(タウロス円形劇場とカリグラ円形劇場)に続く、ローマ初の本格的な恒久円形劇場であり、カンパニア地方に最初の円形劇場が建設されてから実に150年後のことだった。 ティトゥスはさらに3階席と4階席を増築し、80年に100日間にわたる演劇祭で正式に開館した。その後間もなく、ウェスパシアヌスのもう一人の息子である皇帝ドミティアヌスによって大規模な改修が行われ、おそらく金メッキを施した青銅製の盾で飾られた「アド・クリペア」の完成、おそらく「マエニアヌム・スッムム・イン・リグネイ」の追加、そして闘技場の地下通路の建設が彼の功績とされる。 これらの改修後、円形闘技場は海戦劇(ナウマキア)の舞台として使用されなくなった。歴史資料によれば、その直前に海戦劇が上演されていたとされる。
円形闘技場の建設と並行して、競技のためにいくつかの他の構造物が建てられた:ルディ (剣闘士の兵舎兼訓練場として使用されたマグヌス、ガリクス、マトゥティヌス、ダキクス)、ミセノに駐屯しヴェラリウム(帆船)を運用するローマ艦隊クラシス・ミセネンシスの水兵部隊のための兵舎(カストラ・ミセナティウム)、スッムム・コラギウム、武器・装備倉庫(アルマメンタリウム)が建設された。 また、戦傷を治療するサナトリウムと、戦死した剣闘士の遺体を保管するスポリアリウムも設けられていた。 この建造物は多心楕円形をしており、最長軸は527メートル、最広軸は187.5メートル、二軸間の長さは156.5メートルである。円形闘技場内部の寸法は86メートル×54メートルで、総面積は3,357平方メートルとなる。
現在地表に聳える構造物の高さは48メートルだが、元々は52メートルあった。楕円形の壮大な輪郭線と精緻な施工手法は、帝政初期ローマ建築・工学設計の本質的な自然原理を如実に物語る。アーチとヴォールトは構造的に興味深い相互関係にある。古代にはここで剣闘士試合が開催された。 観客は様々な種類のショーを鑑賞できた。動物狩り、海戦劇(ナウマキア)、有名な戦いの再現、神話に基づく劇などである。6世紀以降使用されなくなったが、時を経て様々な用途に転用され、特に採石場として利用された。今日ではローマの象徴であり、見学可能な考古学的記念物として、同市の主要な観光名所の一つとなっている。
 古代ローマ帝国コロッセウム
古代ローマ帝国コロッセウム
帝政時代
ネルワ とトラヤヌスの治世における修復事業は複数の碑文によって確認されているが、修復の第一段階が始まったのはアントニヌス・ピウス帝の治世下であった。 217年、おそらく落雷による火災で上層構造が損傷し、217年から222年までの5年間、コロッセオは閉鎖されました。その間、競技はチルコ・マッシモで開催されました。ヘリオガバルス(218-222)によって始められた修復は、アレクサンダー・セウェルスによって続けられ、彼はスマ・カヴェアの列柱を再建しました。
222年に建物は再開されましたが、修復が完全に完了したのはゴルディアヌス3世の治世になってからでした。この事実は、2人の皇帝の硬貨によって裏付けられているようです。 250年に再び落雷による火災が発生し、デキウス皇帝は修復を命じました。410年にアラリック率いる西ゴート族がローマを略奪した後、修復工事の一環として、競技場を取り囲む観覧席にホノリウス皇帝を称える碑文が追加されたと考えられています。剣闘士試合を廃止し、後に競技場で狩猟ショーの開催を許可したのはホノリウスでした。
この碑文は後に撤去され、442年の地震後の大規模修復を記念して、都市長官フラウィウス・シネシウス・ゲンナディウス・パウルスとルフィウス・ケキナ・フェリクス・ランパディウスの下で再設置された。コンスタンティウス2世はこの改修を大いに気に入った。 さらに470年には、別の地震の後、執政官メッシオ・フェボ・セウェルスによって修復が行われた。西ローマ帝国の滅亡後も工事は続き、484年か508年のいずれかの地震の後、当時の都市長官デキオ・マリウス・ベナンツィオ・バシリオが自ら修復費用を負担した。
獣狩りはテオドリックの時代まで続いた。グラドゥスにはオドアカー時代の元老院貴族の家名が刻まれている。これは古来の慣習だが、クラリッシミ、スペクタビリス、イルストレスといった様々な席次順に従い、新たな居住者の名前に常に塗り替えられていた。現存するのは帝国崩壊直前の最後の刻銘のみである。

中世から近代へ
6世紀には墓地として、後に城塞として使用された。6世紀から7世紀にかけてコロッセオ内部に礼拝堂が建立され、現在ではサンタ・マリア・デッラ・ピエタ・アル・コロッセオとして知られる。847年頃、教皇レオ4世の治世中に発生した地震により構造物に深刻な損傷が生じた。
1349年の大地震では主に南側外壁が崩壊した——この部分は地盤の弱い沖積土の上に築かれていた。13世紀には採石場として利用され、フランジパーネ家の宮殿も敷地内にあったが、後に解体された。しかしコロッセオが無人になったことはなく、その後も多くの住居が設けられた。 15~16世紀には、新たな建造物建設に伴いトラバーチン石が体系的に撤去された。1451年にはコロッセオのトラバーチン、アスプロニ石、大理石が採掘・砕かれ、教皇ニコラウス5世の石灰窯へ運ばれた。この作業はジョヴァンニ・ディ・フォリア・ロンバルド師の指揮下で実施された。
地面に落ちた石材は、1634年のバルベリーニ宮殿建設に、また1703年の地震後はリペッタ港の建設に利用された。ベンヴェヌート・チェッリーニは自伝の中で、コロッセオの境界内で呼び起こされた亡霊たちとの恐ろしい一夜を記し、この場所がいかに邪悪で不吉であるかを証明している。 1675年の聖年(ジュビリー)には、この地で苦難を耐えた多くのキリスト教殉教者を記念し、聖地として奉献された。1744年、教皇ベネディクト14世の勅令により略奪が止められ、敷地内に十四の十字架の道(ヴィア・クルチス)の礼拝堂が建立された。1749年にはコロッセオをキリストとキリスト教殉教者に捧げる教会と宣言した。
近代:19世紀の再現
コロッセオは既に二度にわたる大規模発掘が行われていた——最初に1811年と1812年に古代遺跡委員カルロ・フェアによって、次に1874年から1875年にピエトロ・ローザによって——これにより18世紀半ばまで様々な想像力豊かな再利用計画の対象となっていた。
19世紀末、数世紀にわたる使用(壁内でのキリスト教礼拝やトラバーチン採石場としての利用を含む)を経て、この巨大建造物は極めて不安定な基礎状態に置かれていた。最も顕著な問題は、現在の道路(ラテラノのサン・ジョヴァンニ通りとフォリ・インペリアーリ通り)に隣接する区間、特に大規模修復が行われた箇所で、外周リングが急激に不連続になっている点である。 フェアはまた、石材に穿たれた穴の起源と思われる事象を記録している。おそらく石材を固定していた金属製クランプを抜き取るための機構の一部であったと考えられる。

現在の名称の由来
コロッセウムという名称が中世初期に普及したのは、おそらく当時の1階建て・2階建て住宅が立ち並ぶ中で、ラテン語の形容詞「colosseum」(巨大な)が俗語化した結果である。しかし、より可能性が高いのは、近隣にネロ皇帝の巨大な像が存在したことに由来する説である。 この建造物はすぐに帝国の都の象徴となり、そこではイデオロギーと祝祭への渇望が、公共の娯楽と歓楽の基準を形作った。
近くには巨大なネロの青銅像が立っており、コロッセウムの名はこの像に由来するとされる。この関連性は中世以来記録されており、建造物の巨大な規模も指している。ネロの死後、像は太陽神ソル・インウィクトゥス(不敗の太陽神)へと変容し、頭部には太陽の光線を放つ冠が追加された。 126年、ハドリアヌス帝は金宮(ドムス・アウレア)の中庭にあった像を、金星とローマの女神神殿建設のため移設した。
移設後の巨像の基礎位置を示す現代の凝灰岩台座が残されている。帝政時代にはネロの巨大像は撤去されており、6世紀の人々がそれを記憶していた可能性は低い。14世紀、公証人兼判事アルマニーノ・ダ・ボローニャはコロッセオを「世界最大の異教聖地」と評した。
彼の言葉は「コロッセオが魔術師や悪魔崇拝者の様々な宗派の本拠地となっていた」ことを意味し、近づく者には「Colis Eum?(彼を崇拝するか?)」と問われた。後に教皇ベネディクト14世はコロッセオを浄化のための悪魔祓いを行い、キリストと全ての聖人の苦難を記念する新たな用途を与えた。

構造
基部は周囲の土地より高く盛り上げられた石床の上に築かれている。その基礎は厚さ約13メートルの巨大な凝灰岩の塊に据えられており、外側は煉瓦壁で覆われている。支持構造はトラバーチン石の柱で構成され、ピンで連結されている。建物が廃れた後、これらの金属部品を溶解再利用するために取り外す習慣が生まれたため、柱は接合部で掘り出された。
これが外部ファサードに多数の穴が見られる理由である。柱は下部で凝灰岩ブロック、上部で煉瓦で構成された壁によって連結されている。客席(カヴェア)は台形の樽型ヴォールトとアーチによって支えられており、これらはトラバーチン柱と凝灰岩または煉瓦製の放射状仕切り壁の上に載っている。外部ではトラバーチンが使用されており、客席を支える一連の同心円状に見て取れる。
これらのカーテンウォールは、柱頭で縁取られた一連のアーチで装飾されている。交差アーチ型ヴォールトはローマ世界でも初期の例に属し、オプス・カエメンティキウム(コンクリート積)で造られ、裏打ちにも用いられた交差煉瓦アーチのリブを頻繁に備えている。さらに、外側の二つの回廊の外側にある放射状壁は凝灰岩ブロックで補強されている。 高度な給排水システムが建物の維持管理を支え、観客席に設置された噴水へ公衆向けの水を供給していた。

外部ファサード
外部ファサード(高さ48.50メートル)はトラバーチン製で、ローマ世界の娯楽建築に典型的な様式に従い四段構成となっている。下部の三層は半柱式の柱で支えられた80のアーチで構成され、第四層(アティック)はアーチの柱に対応するピラスターを備えた実壁で形成されている。 各階の柱はそれぞれドーリア式、イオニア式、コリント式である。最上階もコリント式である。
ピラスター間の壁面には40個の小さな正方形窓が配置され、2ベイごとに1つずつ(固いベイには常に青銅のクランプが取り付けられていた)。窓の上部には、各ベイに3つの突出したコンソールがある。 これらのコンソールには天窓開閉用の木製ロッドが収納されていた。おそらく傾斜した石ブロック列で地面に固定されていた。これらの入口は現在もコロッセオが立つトラバーチン石段の外縁部で確認できる(チェリオ側のものは明瞭に見える)。最初の段状レベルには80の入口があり、楕円軸に沿った4つの特別入口を含む。
短軸側には貴賓席(皇帝専用入口)への入口が、長軸側には闘技場へ直接通じる入口が配置されていた。各階は異なる社会階級に割り当てられていた。皇帝は午前中はコンスタンティヌスの凱旋門を向いた観覧席に、午後は現在の地下鉄駅を向いた観覧席に着席した。2階と3階のアーチは、立方体の基部を持つ半柱で構成された連続した欄干で囲まれていた。
半柱と壁柱の4様式は下から順に、トスカーナ式、イオニア式、コリント式、滑らかなコリント式の柱頭を備えていた。最初の3様式は同一の順序で繰り返され、この配列はマルケッルス劇場の正面にも見られる。硬貨には、平面図の楕円軸両端に小さな大理石の柱廊で装飾された4つのアーチが描かれている。

ヴェラリウム
コロッセオにはベラリウムと呼ばれる布製の屋根が設けられており、マンツィオーネら一部の学説によれば、多数の布で構成され観客席を覆いながら中央の闘技場は空に開放されていた。これにより観客に日陰を提供できたのは正午のみであり、その他の時間帯には観客席の異なる部分が直射日光に晒され続けた。他の学者(ダンナとモラーリ)は闘技場を含む完全覆いの形態を提唱している。ヴェラリウムは観客を日差しから守るために設計され、コロッセオの隣に拠点を置くミセノ艦隊の船員たちによって操作されていた。
布を固定するために、ロープと滑車からなる精巧なシステムが使用されていた。マンツィオーネらは、コロッセオ外部の石ブロックに固定されたロープ全体で支えられていたと考える。その一部は現在も確認できる。しかし、最近周辺を掘削したところ、これらのブロックには基礎がないことが判明し、この説は棄却された。

講堂および公共エリアへのアクセス
観客席(カヴェア)は大理石の座席と階段で構成される。全面大理石製で、プレシンクティオネス(仕切り)またはバルテア(区画)によって五つの水平区画(マイニアナ)に分けられ、観客の階級に応じて割り当てられていた。階級は上層になるほど低くなり、上層ほど身分が低いとされている。 上部には木製座席(サブセリア)用の幅広で低い階段があり、元老院議員とその家族が着席した。これらの下段座席を割り当てられた元老院議員の名は、ポディウムの欄干に刻まれていた。 次に約20段の大理石階段からなる第一メニアヌム(maenianum primum)、さらに下段(imum)と上段(summum)に分かれた第二メニアヌム(maenianum secundum)があり、各段は約16段の大理石階段であった。観客席を冠する列柱回廊(porticus in summa cavea)内部には約11段の木製階段があった。
現存する建築構造はセウェルス朝またはゴルディアヌス3世時代の改修に属する。アウグストゥス帝の時代から、女性たちは屋根付きのこの階段席に他の観客と分離して着席していた。 最も望ましくない席は列柱上のテラスで、最下層の平民階級が立つための場所が確保されていた。 観客席への階段と入口は 縦方向に区域を分割し、2世紀の修復時に設置された大理石の仕切りで保護されていた。 短軸の両端(正面区画に先行する部分)には、重要人物用の二つのボックス席があったが、現在は消失している。一つは「S」字形の皇帝・執政官・ウェスタルの処女たちのための席、もう一つは都市長官(プレフェクトゥス・ウルビ)やその他の高官のための席であった。彼らは正式な入口アーチを通り抜けた後、それぞれの席へ向かった。
皇帝や高官は楕円形短軸上の専用通路を利用し、長軸中央の通路は役者や主要出演者専用であった。 その他の観客は全員、チケット番号に従ってこのアーチの下で列をなす必要があった。そのため各公共アーチの頂石には番号が刻まれていた。このような番号付けにより、各自の座席への移動が容易かつ迅速になった。コロッセオのアーチに刻まれた番号は、遠方からも視認しやすくするため赤く塗られていた。
この細部は、トッズ・グループが資金提供した修復作業中に明らかになった。外壁を水噴霧で洗浄し、汚れやスモッグの堆積物を除去した結果、非常に薄い色の痕跡が浮かび上がったのである。ここから、一連の交差する階段が、アーチ型の円形回廊の対称的な配置へと続いていた。 各通路は、フラウィウス朝時代の原形を留める柱頭、大理石張り通路壁、漆喰装飾のアーチ天井で区切られた三分割された楔形空間へと通じていた。さらに皇帝の観覧席南側には、地下回廊を通じ直接外部へ通じる別の入口が設けられていた。 12のアーチは最内周の観客席用回廊に通じており、そこから短い階段が観客席下層部へ下りていた。これらの通路も大理石で覆われていた。残りのアーチは上層部へ通じる単段または二重階段群へのアクセス路となっていた。この区域では壁面は漆喰で覆われ、アーチ天井部分にまで及んでいた。

アリーナと下のサービスエリア
楕円形のアリーナ(86m×54m)は煉瓦と木材で築かれ、砂で覆われていた。この砂は頻繁に清掃され、殺戮者の血を吸収するために用いられた。アリーナは観客席から約4mの高さのプラットフォームで隔てられており、ニッチと大理石で装飾され、青銅の柵で保護されていた。プラットフォームの後方には主要な座席が配置されていた。アリーナ内には、公演時に使用される地下通路へと通じる様々な落とし穴や昇降機が設けられていた。
競技場の下にはサービスエリア(カタコンベ)が広がり、主軸に沿った中央の大通路と、両側に左右対称に配置された12本の曲線状回廊で構成されていた。競技で使用される機械や動物を競技場へ運ぶため、エレベーターが使用された。4本の回廊に分散して80基の昇降機が設置されていた。 現存する遺構から、この建造物は3世紀または4世紀に再建されたことが示されている。ポッツオーリのフラウィウス円形劇場(コロッセオと同じ建築家によって建設された)の地下通路との比較から、コロッセオの地下通路がローマ時代にどのような姿であったかを推測することができる。 ポッツオーリでは、野獣の檻を競技場へ運搬するためにローマ人が使用した装置が今も確認できる。地下通路の天井は失われているため、競技場下の部屋は今日でも視認可能だ。競技場下のサービス施設には独立した入口が設けられていた:
主軸線の終端にある地下通路は、闘技場下の中心通路へと繋がっており、動物や機械類の運搬に用いられた。 主軸上の二つの巨大なアーチ型入口は競技場へ直接通じており、地下通路で運搬できない重量級の動物や主人公(ポンパ)、剣闘士らの入場を可能にした。スタッフはまた、観客席下の観覧席(ポディウム)下部に位置し競技場を囲むサービス通路の開放部からも入場できた。最も内側の円形回廊は、元老院議員が着席したギャラリーへと繋がっていた。

コロッセオのサンタ・マリア・デッラ・ピエタ教会
コロッセオ内部にはカトリックの礼拝所であるサンタ・マリア・デッラ・ピエタ教会がある。フラウィウス円形闘技場のアーチの一つに建てられた簡素な教会である。その起源は6~7世紀と推定されるが、確実な記録が14世紀に遡ることから、その可能性は低い。
この教会は、コロッセオ内で殉教したキリスト教徒を偲ぶ礼拝の場として常に機能し、多くの聖人が訪れています——ロヨラの聖イグナチオ、聖フィリッポ・ネリ、聖カミッロ・デ・レリなど、ほんの一例に過ぎません。 ローマの考古学者マリアーノ・アルメッリーニによれば、「この礼拝堂はもともと、教皇パウロ4世の時代まで円形劇場でキリスト受難劇を上演していた劇団の楽屋として使用されていた」という。したがって1622年、この聖域はゴンファローネ兄弟会の所有となり、同会はここに礼拝堂を建設し、管理人として修道士を配置した。 1936年、ローマ教区はサン・ピエトロ協会にこの教会の典礼管理を委任した。

剣闘士競技
コロッセウムでは円形競技場式のスポーツが行われ、動物闘争(ヴェナティオネス)、野生動物による処刑その他の処刑(ノクシイ)、剣闘士試合(ムネラ)などが催された。これらの行事は決まったスケジュールに従って行われた:午前中は動物同士の闘争、あるいは剣闘士と動物の闘争、正午には処刑、午後には剣闘士試合である。
コロッセオ完成を祝して、ティトゥス帝は3か月にわたる競技会を開催し、約2,000人の剣闘士と9,000頭の動物が参加した。トラヤヌス帝のダキア人に対する勝利を祝う際には、10,000人の剣闘士が参加した。
記録に残る最後の剣闘士試合は西暦437年に行われた。しかし円形闘技場はテオドリック大帝の治世まで動物の殺戮に利用され続けた。最後の剣闘士試合は519年(テオドリックの娘婿エウタリクスの治世)と523年(アニシウス・マクシムスの治世)にそれぞれ行われた。 コロッセオの下水道での発掘調査により、クマ、ライオン、馬、ダチョウを含む多くの家畜や野生動物の遺骸が発見されている。
サービスとアクセシビリティ
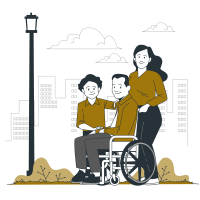
車椅子対応

トイレ

書店

休憩所

ベビーピットストップ

